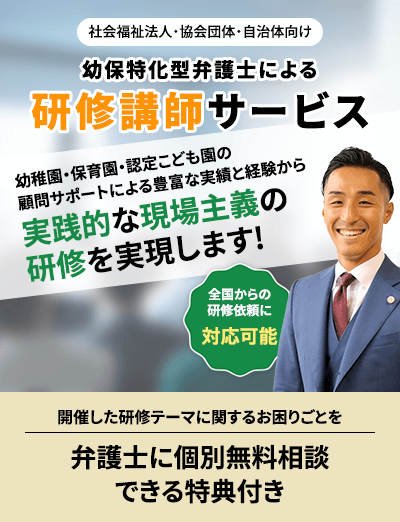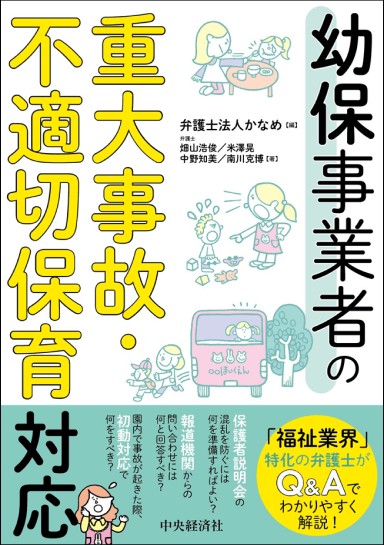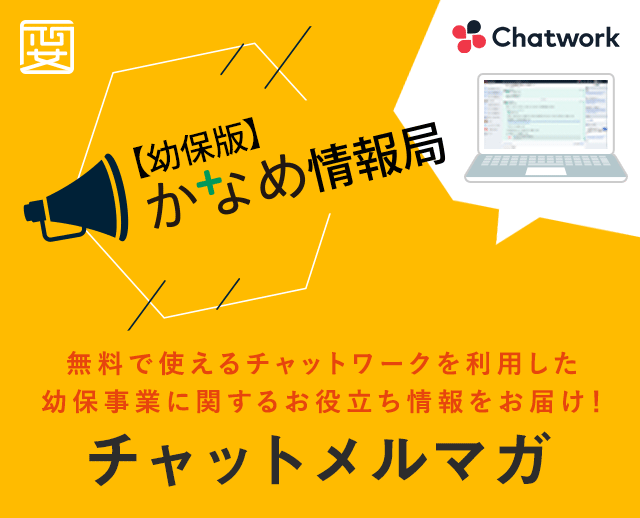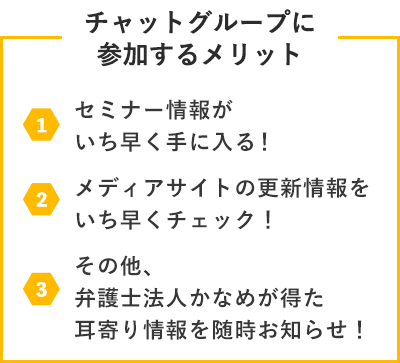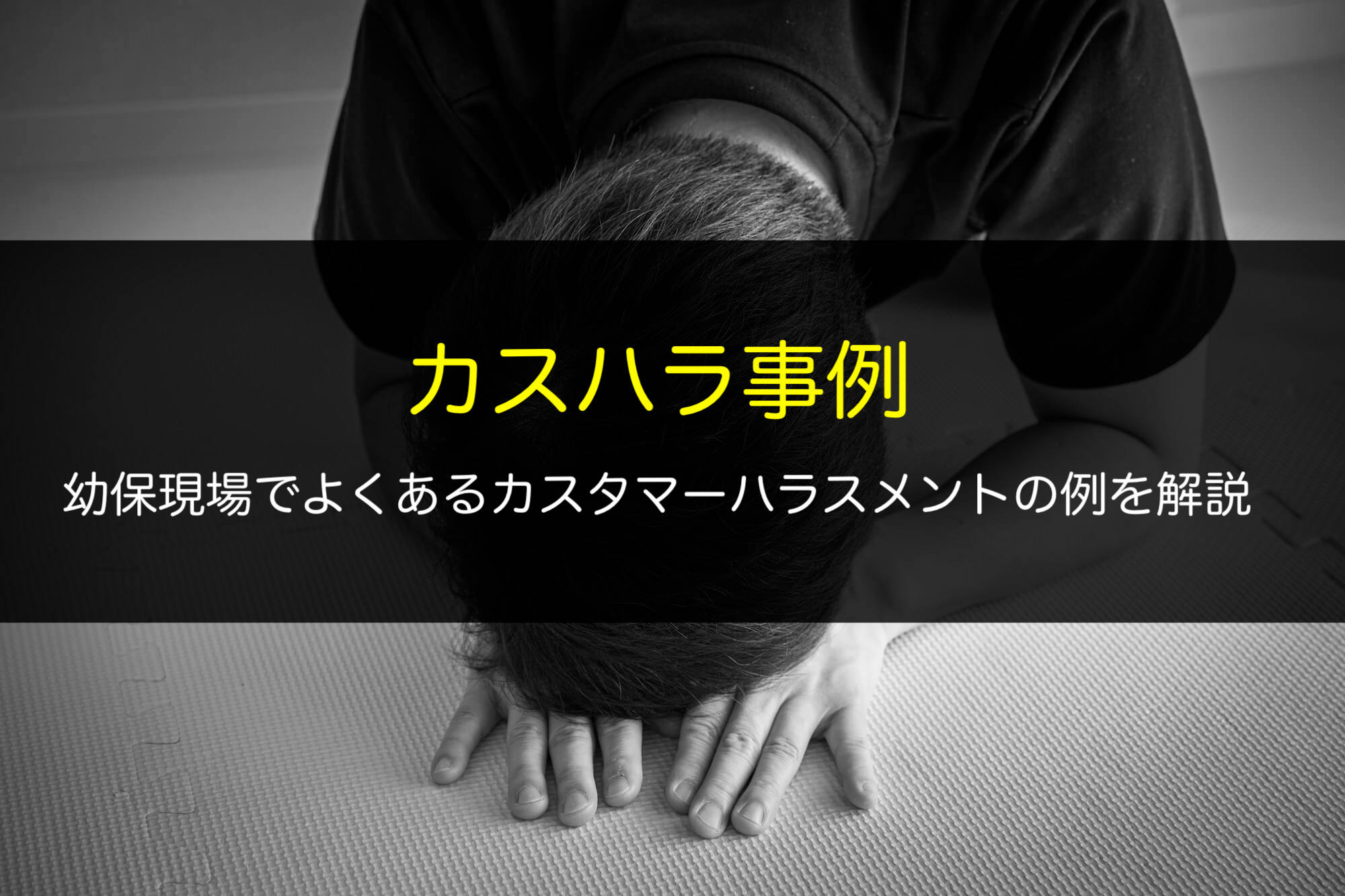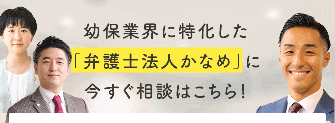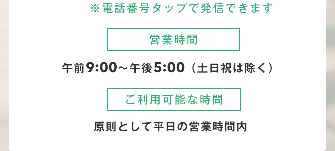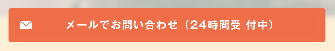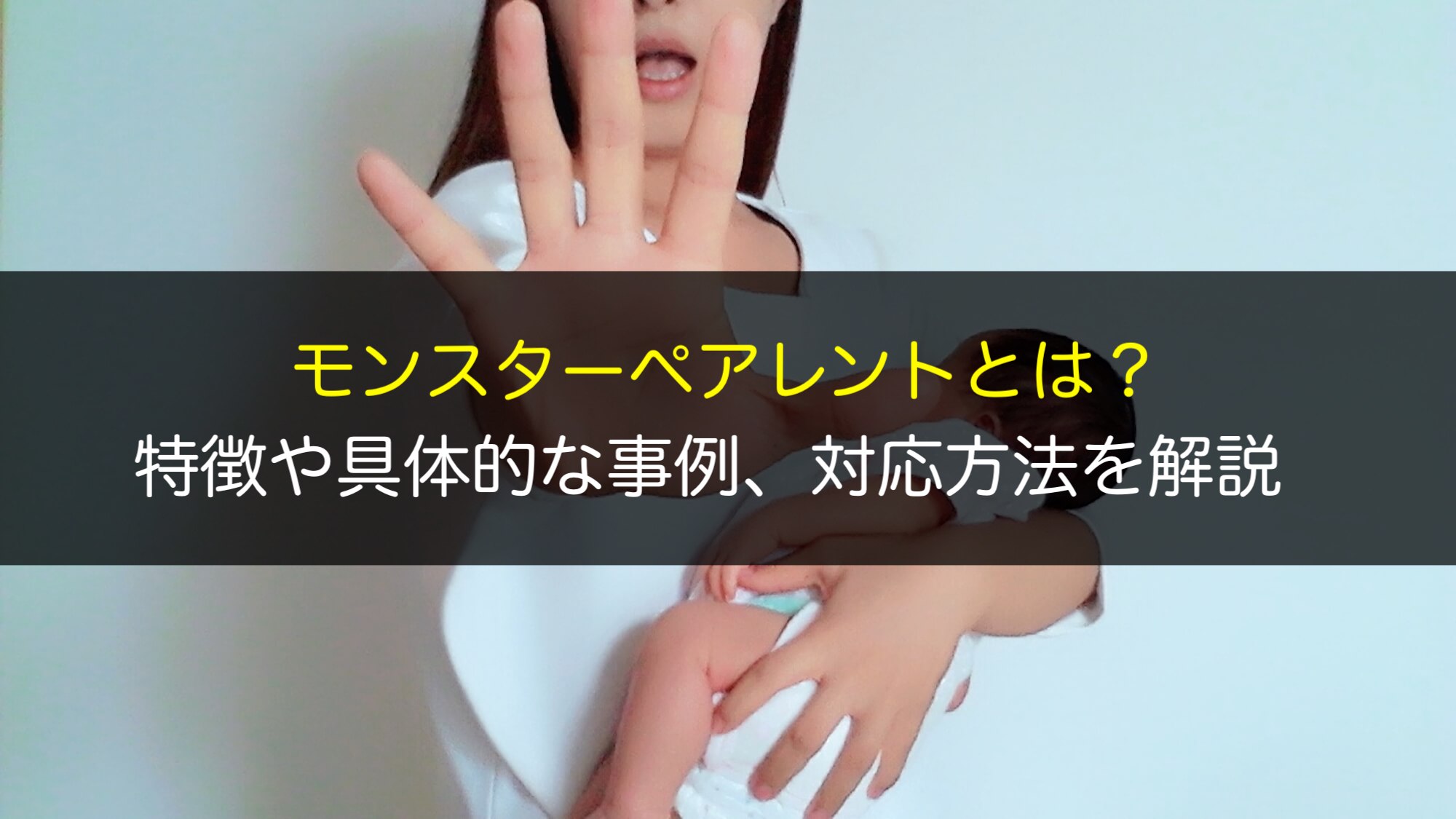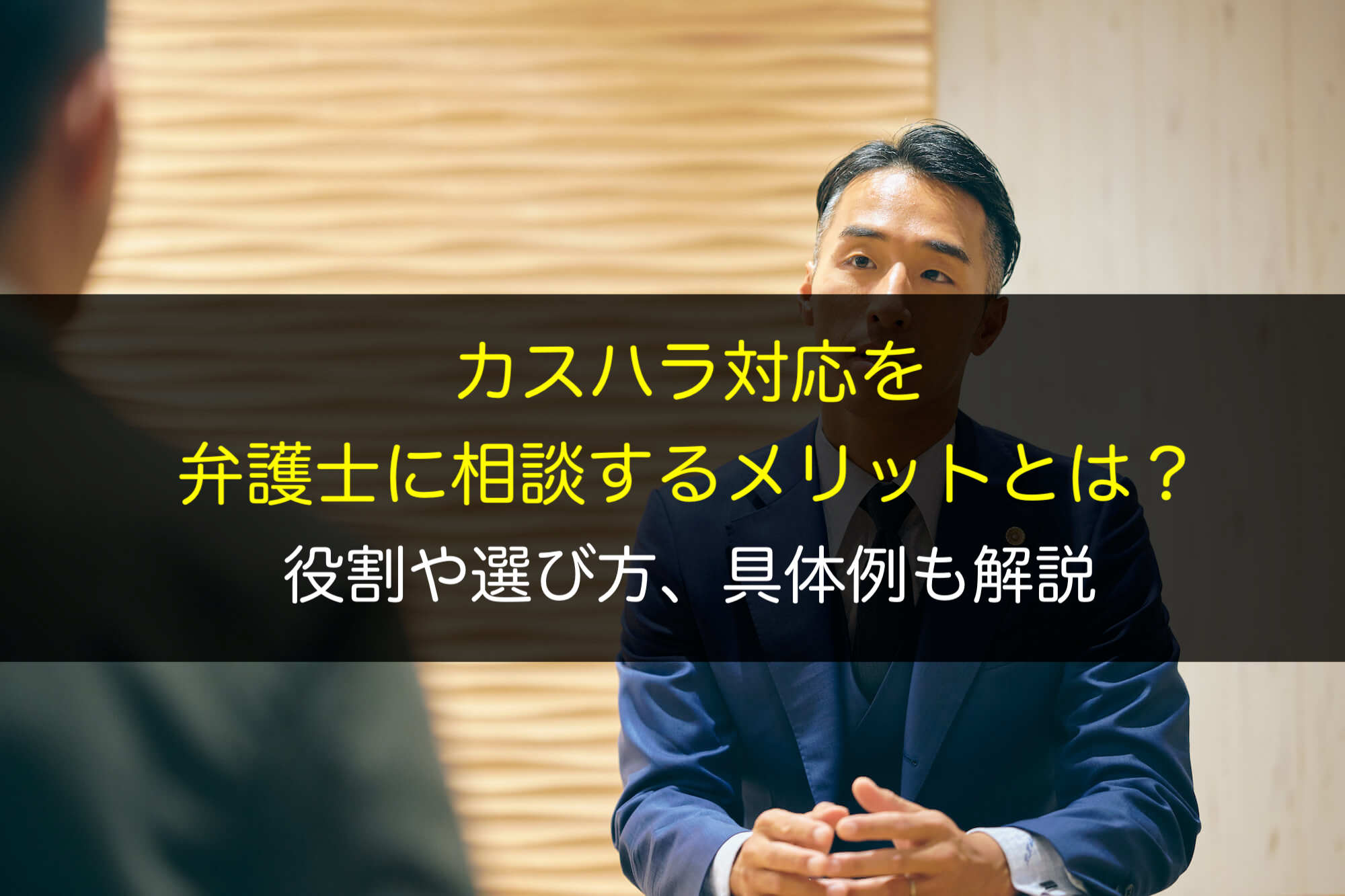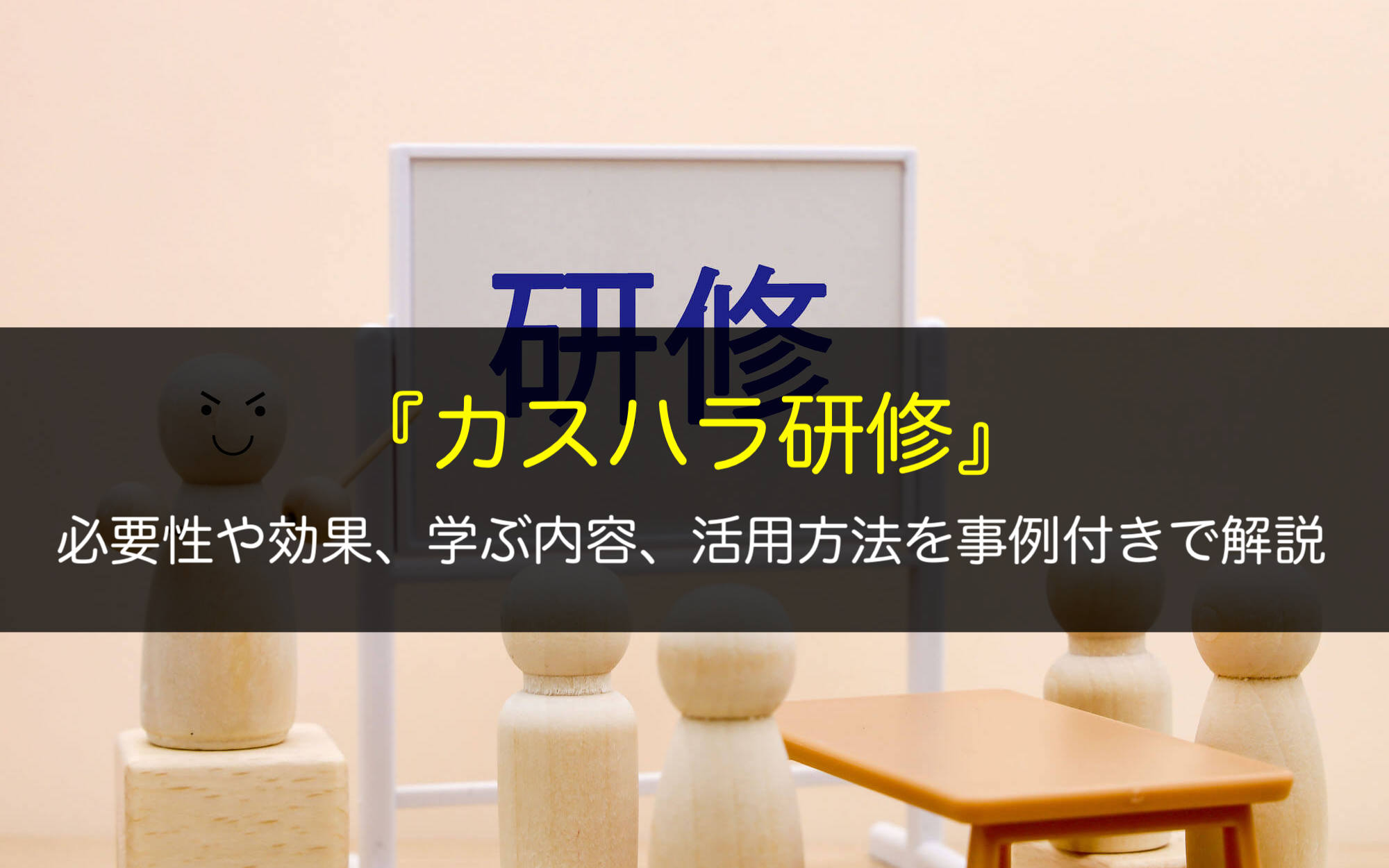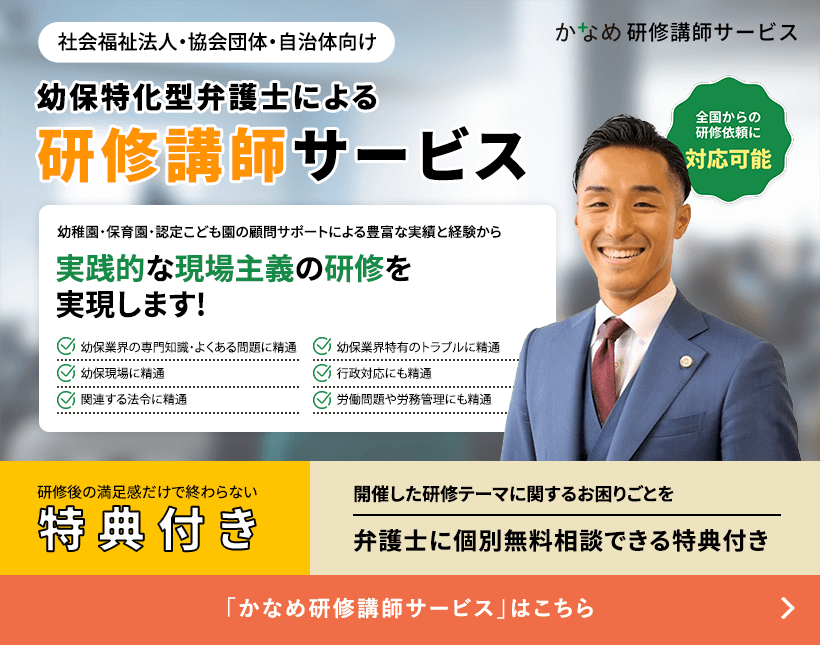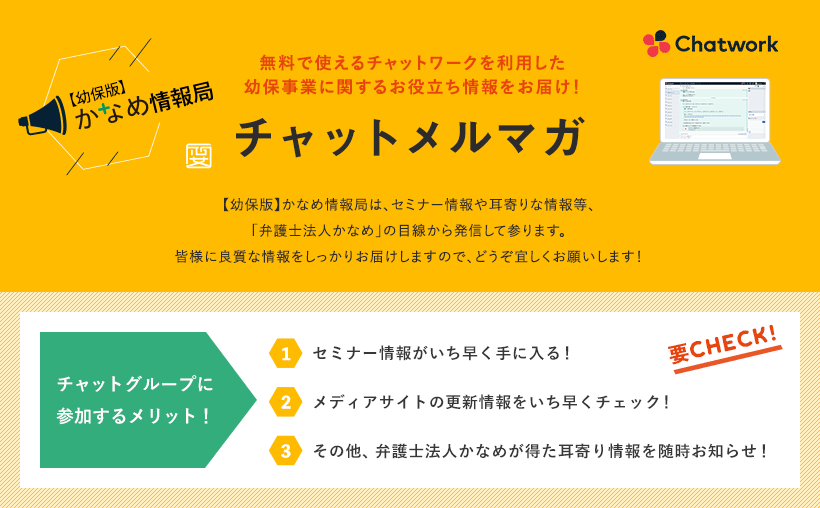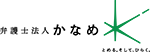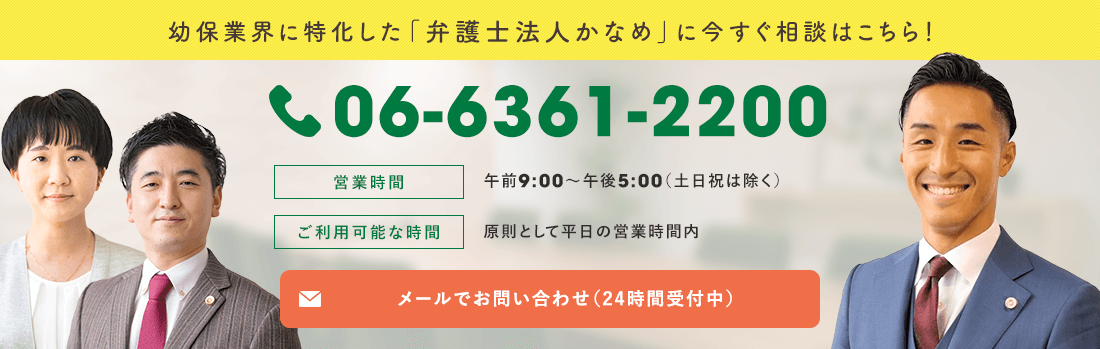
顧客などによる従業員への著しい迷惑行為、いわゆる「カスハラ(カスタマーハラスメント)」は、業種問わず発生している深刻な社会問題です。
近年では、幼保業界でも、職員が保護者から過度な要求や理不尽で悪質なクレームを受けることが増え、ニュースなどで他業種のカスハラが取り上げられるたび、身につまされる思いでいる園の関係者も多いのではないでしょうか。
幼保業界では、充分なカスハラ対策を講じている園はいまだに少ないのが現状です。日常的に保護者からクレームを受けることが多い幼保の現場では、カスハラに対し、次のような疑問や迷いが生まれて判断に苦慮されているのではないでしょうか。
- 「そもそもカスハラとは正確にどういう意味なのだろうか、幼保業界でのクレームも含んでいいのだろうか。」
- 「保護者のクレームは、どこからがカスハラと言えるのか、線引きが難しい。」
- 「保護者が怒鳴ってクレームを言ってきたとしても、内容は正論だから我慢した方がいいのではないか。」
- 「園側に落ち度があったことが事の発端だから、過剰な要求でも今回は甘受するべきではないか。」
クレームの中には、我が子や園のことを思って意見する保護者の声が含まれることもあります。また、園児や保護者とは今後も関係が継続していくことを考えると、カスハラかどうか明確な判断ができず、なんとか温和な解決を図ろうとすることは当然であると言えます。
しかし、カスハラへの対応を誤ると、園の運営や職員の日常業務に支障が出たり、最悪の場合、職員が精神疾患に罹患して離職したりするなど、職員の安全な職場環境は維持できません。
最近では、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)などの改正案が閣議決定され、職場におけるハラスメント行為に対し法的措置も視野に入れて対策を強化する動きがますます進んでいます。改正法が施行されることになれば、事業主には従業員の就業環境を守り体制を整備するなどの対策が全企業に義務付けられることになります。
園や職員を守るために、まずは、どのような事例がカスハラにあたるのかという側面からカスハラを正しく理解し、適切な対策や体制づくりを進めていくことが重要です。
そこで、この記事では、幼保現場におけるカスハラの具体的な事例について、裁判例などを通じて解説します。また、弁護士法人かなめが実際に相談を受けた事例についても、そのアドバイス内容と共に紹介しますので、「これってカスハラなの?」と頭を悩ませている園の皆さんは、是非参考にして下さい。
それでは、見ていきましょう。
【参考情報】幼保事業所で発生したカスハラ対応を弁護士に相談するメリット、弁護士の役割などについては、以下を参考にしてください。
・カスハラ対応を弁護士に相談するメリットとは?役割や選び方、具体例も解説
また、保育園・幼稚園・こども園など幼保業界における弁護士の必要性や探し方、費用などについては、以下の記事で事例付きで詳しく解説していますので参考にしてください。
この記事の目次
1.そもそも「カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?」
カスハラとは、カスタマーハラスメントの略称で、令和7年4月1日に施行された東京都カスタマー・ハラスメント防止条例では、「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。」(第2条5号)と定められています。
また、厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(2022年2月)によると、以下のように記載されています。
“顧客などからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの”
その具体例としては、要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いものとして、暴行や脅迫、威圧的な態度、土下座の強要などの行為、要求内容の妥当性に応じて不相当とされる可能性があるものとして、金銭の要求や商品の交換、土下座を除く謝罪の要求などがカスタマーハラスメントとして列挙されています。
さらに、条例の制定と合わせて、カスタマー・ハラスメントの奉仕に関する指針(ガイドライン)も策定されていますので、こちらも併せてご覧ください。
この記事では後ほど、幼保業界のカスハラ事例について具体的に紹介していきますが、保育園、幼稚園、こども園、学校などの保育・教育現場において、保護者やその関係者から、次のような行為を受けた場合、カスハラとして判断していいでしょう。
- 要求が園にとって対応の義務のない内容であり、そのことを説明したにもかかわらず要求を続ける場合
- 仮に要求自体は、全く義務がないとは言えないことであっても、その要求態様が、執拗で、昼夜問わず長時間の対応を要求してきたり、責任者や職員全員の謝罪を要求してきたり、不必要に職員を罵倒したり暴力を振るってくるような場合
- なんらの要求があるわけではないにもかかわらず、職員を執拗に怒鳴なり、暴力を振るような行動をされる場合
送迎時などに保護者と毎日のように顔を合わせて接する幼保の現場では、カスハラ行為を受けるリスクが非常に高いと言えます。また、カスハラ行為を受けた場合、担任を交代したり登園を拒否したりすることが難しく、その後もそれまでと同じように接する関係が継続するため、職員にとっては逃げ場のないストレスフルな状態となり、心身共に疲弊していきます。
1−1.カスハラ(カスタマーハラスメント)は社会問題
カスハラは様々な業界で問題となっており、事件としても度々報道されてきました。
2014年には来店した客数名が店員の態度に言いがかりをつけ、謝罪として店員に土下座を強要し、その写真や動画がインターネット上に投稿されて世間を騒がせましたが、客らは逮捕され最終的に恐喝の罪で執行猶予付きの有罪判決が下されました。最近では、有名俳優が交通事故を起こし、搬送先の病院で看護師に暴力を振るったことで傷害の疑いで逮捕されたことも話題となっています。
大きな事件にならなくても、世間には数多くのカスハラ事例が存在します。特にコールセンター、飲食店、ホテルや介護などのサービス業、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売業ではカスハラ被害が深刻です。
●コールセンターでの事例
顧客が商品に対する不満を数時間に渡って話し続け、切電の際に受電者の名前を聞き出したうえで、翌日以降も毎日架電し、同じ従業員を指名して通話を長時間続けた。
●飲食店での事例
注文した料理の提供が遅いことについて、顧客が従業員に対し「いつまで待たせとるんや、早く持ってこい!」と大声で威嚇した。
●ホテルでの事例
宿泊客が客室に追加のアメニティを持参するよう内線で指示し、持参した女性従業員の手に触れながら「かわいいね、一緒に寝ようよ。」と発言した。
●スーパーの事例
客からスーパーで購入した刺身から消毒液の臭いがするとのクレームを受け、従業員が自宅まで同等の商品を持参したが、店長による謝罪と謝罪金を要求した。
こういった行為は従業員に精神的なダメージを与え、本来の業務や他の顧客へのサービス提供にも悪影響を及ぼします。他にもカスハラの事例集として厚生労働省が公開しているものがありますから参考にしてみてください。
1−2.カスタマーハラスメントに対応する意義
次にカスハラに対応する意義を考えてみましょう。
まず、園としてカスハラへの適切な対応を怠り、現場の職員に対応を丸投げしてしまうと、その職員が疲弊してメンタル不調となり、うつ病など精神疾患の発症や、最悪の場合には離職につながる場合もあります。さらには、園に対して、精神疾患を発症するなどして離職した職員から、労働契約上の安全配慮義務違反があるとして、損害賠償請求をされるなど法的責任を追及される可能性もあります。
また、慢性的な人手不足に悩む園にとっては、職員の離職は死活問題です。職員の離職や、カスタマーハラスメントへの対応に職員の時間を割かれることで、正常な園の運営を実施できず、本来時間を注ぐべき子供たちへの保育・教育サービスを十分に提供できないなどの問題も発生し得えます。
このように、カスハラに適切な対応をとらないことは、多くのリスクに直面する可能性があり、また雇用主として、従業員が安心して働ける環境を作り、貴重な人材の流出を未然に防ぐため、園が早急に取り組んでくべき課題なのです。
1−3.幼保現場でのカスハラ(カスタマーハラスメント)の特徴
それでは、幼保現場でのカスハラの特徴はどのようなものか、分析したいと思います。
(1)保護者の状態
同じカスハラと言っても、幼保現場での保護者対応と、その他一般企業での顧客対応においては大きな違いがあります。それは教育・保育サービスを直接に受けるのは保護者ではなく子供(園児)であって、大抵の場合、クレームの内容に子供が介在するということです。
保護者の中には、園の運営改善に活かされ、保育・教育サービスの向上に繋がるような通常の正当なクレームを言ってくれる人もいますし、子供の怪我に関わるようなことであれば、親として感情的になってもおかしくありません。
しかし「うちの子が別の園児から怪我させられて酷い目に遭わされた、保育士が見ていなかったなんてどういうことや!土下座して謝罪しろ!」、「うちの子は〇〇先生のことしか信頼していないので、来年度のうちの子のクラス担任は〇〇先生にしてくれないと困ります!」といった、我が子のためと言って、自分の感情を爆発させたり園の運営や方針にまで過剰に介入したりする行為は正常ではありませんから、クレームの内容やクレーム時の保護者の言動の態様をよく見極める必要があります。
また、保護者によっては、クレームに誠実に低姿勢で対応にあたる職員を見て、自分が優位な立場にあるように錯覚し、かえって自己中心的な態度に取って代わり、理不尽な要求を押し通そうとカスハラ行為にエスカレートさせる場合もありますから、対応には注意が必要です。
(2)対応すべき相手は父母だけではない
理不尽で悪質なクレームを言ったり、威圧的な態度をとったりするのは、園児の父母だけとは限りません。園児の祖父母や叔父叔母などの親族や、時には園児の家族と仲が良い友人までもがカスハラ行為をすることがあります。
そういった親族や、保護者の友人などといった当事者から遠い人物が出現すると、対応しなければならない相手の人数が増えるため、必然的に把握しなければならない情報量が増えます。そうすると、職員間に混乱が生じたり、相手によって職員の発言内容が微妙に変わることで揚げ足を取られ、ハラスメント行為がエスカレートしたりする可能性があります。園としては、対応窓口を一つに絞り、情報を統制するなど、対応に十分注意する必要が出てきます。
(3)契約解除の難しさ
一般的な企業の場合、カスハラ行為をする顧客や取引先に対し、最終的な手段として、入店を拒否したり通話の途中で切電したりするなどして、対応を打ち切るという選択が可能です。では、幼保業界ではどうでしょうか。
利用にあたって、施設・事業者と保護者の間には契約関係があるため、保護者が園の運営規程等に沿わない場合、園から退園を勧告し、契約を解除することが可能です。
しかし、認可保育施設等の場合は注意が必要です。例えば認可保育園は、公立・私立を問わず保護者と市町村間での利用契約(ただし公立保育所の場合は保護者と施設間の公的契約)が並行して存在します。また、子ども・子育て支援法は、「特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」として、いわゆる応諾義務を規定していることから、「正当な理由」がある場合を除き、利用を拒否することができないとされています。
そしてこの「正当な理由」というものが大変厄介になります。
子ども・子育て支援新制度ハンドブックでは、正当な理由として
- ①定員に空きがない場合
- ②定員を上回る利用の申し込みがあった場合
- ③その他特別な事情がある場合
を挙げ、このうち、「③その他特別な事情がある場合」については、「特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業の受入能力・体制との関係」「教育・保育提供エリアの設定との関係」「利用者負担の滞納との関係」などについて、慎重に整理し、運用上の取り扱いを示すに止まり、保護者とのトラブルなどについて明確で具体的な基準を設定していません。
園が、事前の入念な準備なく、保護者の迷惑行為を理由として退園させようとしても、保護者が納得せずに行政に通報すれば、正当な理由があるかどうか行政の調査が入ることなどが想定され、結果的に退園させるに至らない可能性もあります。
カスハラ行為を正当な理由として退園させる場合は、カスハラ行為の事実について客観的な証拠を収集し、保護者に通告することと並行して行政にあらかじめ連絡しておくなどの準備が必要になるのです。
また、利用契約の解除に伴うトラブルを未然に防ぐため、利用契約書や園則などに契約の解除事由(退園理由)をあらかじめ記載しておくことが重要となりますが、園によっては法的な整備が不十分であることも多く、いざという時に対応に苦慮するケースが見受けられ、契約解除を困難にしています。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
利用契約の中に解除事由を定めたからと言って、必ずしも委任契約を解除ができるわけではないことには注意が必要です。
解除をするためには、上記の正当な理由のほか、継続的契約であることから、信頼関係の破壊があることなどが必要となり、仮に形式的に解除事由に当てはまっていてもそれだけで解除ができるわけではありません。
もっとも、利用契約の中に解除事由の具体的な記載があることで、これを理由に職員から相手方に対して注意をしたり、警告をしやすくなります。
2.幼保現場での保護者からのカスハラ事例
次に、幼保現場ではカスハラ行為に関して様々な事例が存在しますが、ここでは要求内容自体が不当なケースと要求の手段・態様が不当なケースと大きく2つに分類して紹介します。
2−1.事例1:過剰または不合理な要求(要求内容自体が不当)
- 保護者が園児が工作中に絵の具でブランド品の着衣を汚したことを理由に、金銭的な弁償を求めた。
- 演劇で使用する衣類を家庭で用意するように予め保護者へ書面で通知し、口頭でも依頼していたにもかかわらず、書類は園児の鞄に入っておらず口頭でも知らされていないとして、園で準備するよう要求した。
- 保護者が会社に遅刻することを理由に、受け渡し前に済ませるべきオムツ替えを保育士に要求した。
- 保護者が我が子の箸の使い方やボタンかけの発達が遅いことを園の教育方法に問題があるとして、我が子に対し指導するよう求めた。
- 保護者が通勤電車の時刻が送迎の時間に間に合わないという理由で、10分間の延長保育料を無料にするよう求めてきた。
このように、本来、園では応じる義務のない無理な要求を突きつけたり、保育・教育方法に過度に介入してきたりする行為は大変多く見受けられます。幼保サービスは、保護者の生活や子育てそのものに密接に関連しており、日頃から密に園児に関わる情報を密に交換することも多いことから、保護者と職員の関係は近く、保護者は職員に対して甘えが生じやすくなっています。
また、次のように他の園児と比較して、自分の子供が有利となるよう求めたり、子供の自主性を尊重せずに園の指導に干渉してきたりするような過干渉で過保護な要求もカスハラ行為に含まれます。我が子のための要求と言っても、正当な理由はなく内容は妥当性を欠いています。
- 集合写真を撮る時は、背が低い我が子を一番前にするよう保護者が要求した。
- 我が子が朝食をとっていないことを理由に、登園後に補食を提供するよう要求した。
- 保護者「うちの子がAちゃんからいじめられていると言っている、Aちゃんだけでなく、うちの子がいじめられているのを見て見ぬふりをしているすべての園児とその保護者を注意してほしい。」と要求した。
こういった要求内容そのものが不当な場合、明らかに提供する教育・保育サービスから外れた要求には対応できない旨を毅然と保護者に伝えるべきですが、すぐに判断できない場合は、まずは保護者の主張や要求の内容を聞き取り、客観的事実関係等の確認を行います。確認の調査を踏まえ、要求内容の正当性について判定し、保護者に回答しましょう。
要求内容が正当であると判断した場合は、園内で正当なクレームとして周知し、サービス内容の改善に繋げます。要求内容が不当であると判断した場合は、保護者に対し毅然とした回答を繰り返し、それでも要求が止まずエスカレートする時には、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。また、回答する際には複数人で対応にあたり、一人はメモを取る係となって会話の内容を記録しておきましょう。
参考事例:実際に、過剰な要求などのカスハラ行為を繰り返した保護者とのトラブルが裁判にまで発展した事例
この事案は、保護者が園に対して、過剰で細かな要望や、教育方法に対する不合理な苦情を続けたため、園は信頼関係が完全に破壊されたと判断し、保育委託契約を締結してから1年経たずして、保護者に対し退園通知書を送付して保育委託契約を解除したものの、契約解除は園の不法行為や債務不履行に原因があるにもかかわらず一方的に園が行ったものとして、保護者が訴訟を提起した事案です。
原告の保護者は、パン給食や体育指導などについて、園が入園前に虚偽の説明をし、園児のマスクの着用やトイレ指導についても、職員が園児に対して強制や虐待を行ったなどと主張していました。
原告の保護者は、無添加にこだわりがあり菓子パン類が提供される日に別のパンを持参することや、子供がアレルギーではないにもかかわらずパン給食やメニューによってキャンセルすることを希望し、体育指導では家庭で子供が嫌がる発言をしていることを理由に、跳び箱や鉄棒などをさせないよう要望するなど、園としての集団生活における指導方法や園児の自発的な成長を促すような教育方針に沿わない要望を繰り返していました。
訴えられた園は、家庭教育との連携を図り、園児の発達状況に応じて柔軟に対応を続けていましたが、保護者の不当な要望に応じるわけにいかず、自園の保育体制や職員の精神面でも園児の在園を継続することに限界を迎え、やむをえず契約解除したものです。
裁判所は、園側からの主張を認め、原告の保護者からの請求を棄却しました。
園の対応に落ち度があったとは考えられませんが、問題が悪化していく中で、弁護士などの専門家が介入し直接保護者に対応するなどしていれば、裁判に移行せずに済んだかもしれませんから、カスハラについては早めに専門家に相談することをおすすめします。
▶参考:大宮簡裁令和4年7月7日判決
●事案の概要
原告らが各自被告に対し、原告らの子供(令和3年7月当時4歳)を通わせていた被告の運営する幼稚園から子供を一方的に退園させられたとして、準委任契約の解除に基づく損害あるいは不法行為(名誉棄損を含む)及び債務不履行に基づく損害の賠償を求めた事案
●裁判所の判断
裁判所は、原告らは、幼稚園のしおりや園児募集要領を入園前に受領し、被告側からの説明も受けたうえで、園の教育方針や保育内容、保育料を含めた必要経費、教職員の配置状況等の具体的な条件を検討した結果、入園を決定したものであるから、原告らの子供が退園するまでの経緯を総合的に見て、給食パンの説明が事実と異なったからといってそれだけで直ちに被告の原告らに対する不法行為を構成するものということはできないし、原告の主張する被告の虚偽の説明ということに関してはいずれも不法行為あるいは債務不履行と認めることはできず、本件契約に関して被告に不法行為あるいは債務不履行の事実は認めることはできないと判断しました。
また、裁判所は、原告らが家庭の教育方針(特に食と運動)の実現を被告に要望したものの被告がそれを無条件に受け入れることなく、園としての教育方針を曲げることはできないとして原告らの理解を得るために努力をしたが、結果として日常的なささいな出来事さえも原告らには感情的に映るようになり、子供の保育という本来の目的を達成するのに必要不可欠な相互の信頼まで喪失してしまって結果的に信頼関係が失われ子供の保育を継続するのに困難な程の事態に至った直接的な原因は、原告らからの実現困難な要望、被告の保育態勢を子供への強制とする非難、職員の言動に対する苦情等と認めるのが相当であり、かつ、被告が信頼関係の回復に十分努めた事実も認めるべきであるから、被告には契約を解除するやむを得ない事由があったものと認めることができ、原告らの主張する損害は、いずれも被告の契約解除との因果関係が認められないから返還する必要のないものであるとして、原告らの請求を棄却しました。
2−2.事例2:暴言・脅迫(要求の手段・態様が不当)
- 園児が園庭で怪我をしたが軽傷だったため、園で手当てをして対応したが、保護者が「なんですぐ病院に連れて行かなかったのか、家に来て謝罪しろ!!!」と怒鳴って威圧的な態度で職員を詰問した。
- 保護者が「園庭遊びの時にうちの子園児から目を離しているのを見た、うちの子がケガした時は損害賠償させてもらう。」と職員に述べ、職員は恐怖を感じた。
- そのような事実は確認されていないにもかかわらず、保護者が口コミサイトに”先生が冷たい言葉で叱って園児を泣かせていた、不適切保育が行われている”と書き込みをした。
- 保護者が「帰宅したら子供の体に発疹がある、給食のアレルギー対応を怠ったのではないか、市に通報する!!!」と罵声をあげながら園に電話し、園長が自宅に来て謝罪するよう要求した。
仮に要求自体は、全く義務がないとは言えないことであっても、その要求態様が、執拗で、職員が委縮するような脅迫的な言動は正常ではありません。昼夜を問わない長時間の対応や責任者や職員全員の謝罪を要求する、話し合いの際、職員の様子を動画で撮影する、不必要に職員を罵倒、暴力を振るうケースもカスハラ行為です。また、訴訟などをちらつかせたり、SNSや口コミサイトでネガティブな情報を拡散したりして、園に焦燥感を与えるような事例もそれに当たります。
要求の手段・態様が不当な場合の対応は、「2−1.事例1:過剰または不合理な要求(要求内容自体が不当)」と同様に、要求内容と保護者の言動について事実確認と判定を行ったうえで保護者へ回答するというプロセスになりますが、不当だと判断された場合、保護者へ回答する際に再びカスハラ行為を受けること想定し、複数人で対応にあたり、録音や録画を準備したうえで、弁護士への相談や警察への通報も視野に入れて対応にあたりましょう。
参考事例:保護者によるカスタマーハラスメントを起因として、保育の現場で実際に起きた痛ましい事例
この事例は、園の保護者と元保護者が、帰宅途中の保育士を呼び止め車内に引き込むなどし、保育士らが園児を虐待していると訴えて事実関係の確認を要望したことから始まりました。
後日、園と保護者の間で会合が開かれましたが、会合は「一部の保護者らが,亡Bを含む保育士ら一人一人に対し、虐待行為の有無を確認し、約3時間にわたり,全般に威圧的な態度で追及し、平行線のまま終了したものであり、終了後には憔悴して泣く職員もいた」ようなものでした。
そして、この虐待騒動により強い心理的負荷を受けた保育士が、うつ病を発症し、その影響及びその後の本件保育園における業務による心理的負荷により、その症状が増悪して、失踪し、自殺するに至ってしまったのです。
虐待、不適切保育への対応は、カスタマーハラスメントへの対応と切っても切り離せません。職員を守り、園運営を適切に行うためには、園の方針をしっかり立て、計画的に臨むことが必要なのです。
▶参考:長崎地裁令和3年1月19日判決
●事案の概要
被告法人が経営する保育園に勤務する保育士亡Bの相続人である原告X1ないしX3が、亡Bは、同保育園で発生した虐待騒動等によって業務上強度の心理的負荷を受け、うつ病を発症し、自殺するに至ったなどとして、被告法人に対し、安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案
●裁判所の判断
亡Bは、虐待騒動により強い心理的負荷を受けて、うつ病を発症し、その影響及びその後の本件保育園における業務による心理的負荷により、その症状が増悪して、失踪し、自殺するに至ったとして、本件保育園における業務と亡Bの自殺との間に相当因果関係を認め、また、被告法人は、亡Bが本件保育園における業務による心理的負荷等が蓄積することにより、うつ病等を発症し、ひいては自殺するおそれを予見し得たところ、亡Bの業務負担の程度や健康状態を正確に把握し、心理的負荷を軽減して、健康を維持するための適切な措置をとっていなかったとして、同法人の安全配慮義務違反を認めた上で、同法人主張の諸事情による減額割合を3割とし、損益相殺及び履行猶予に係る被告法人の主張を一部認め、請求を一部認容しました。
3.弁護士法人かなめが対応したカスハラ事例
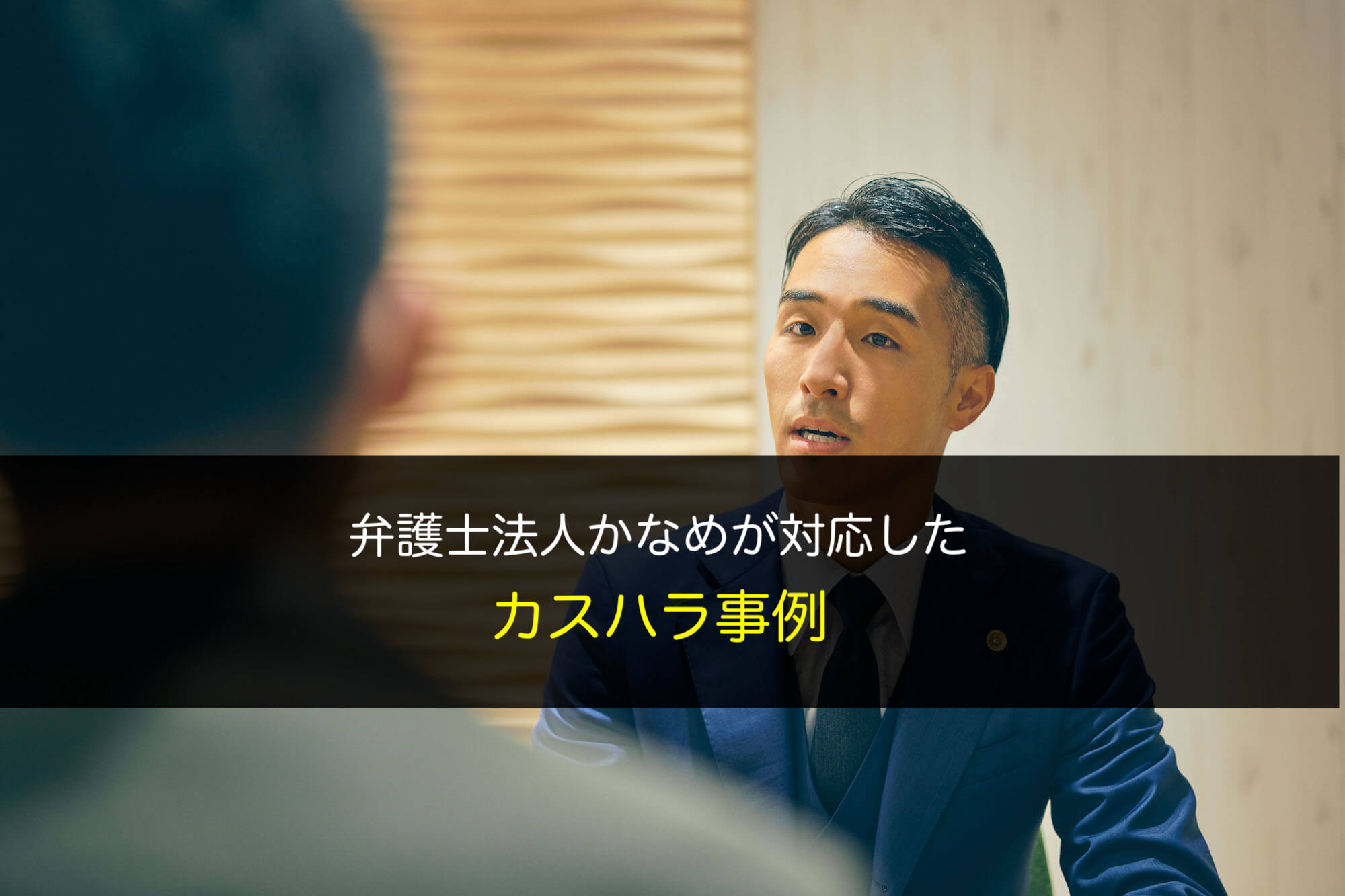
弁護士法人かなめでは、これまでに数々のカスタマーハラスメントに関する相談を受けてきました。具体的には、以下のような相談を受け、対応しました。
3−1.事例1:保育事故に起因して発生したカスハラ事案
(1)事案の概要
園内で、園児の転倒事故が発生し、その後園としては適切な救護措置や保護者への連絡等を行ったが、保護者から「転倒事故は園の責任であるから、治療費の支払いや、治療にあたって登園できず、仕事を休んだ分の休業補償をしろ」と要求された。
保険会社が事故の調査をしたところ、転倒事故について園側の過失等は認定できないということであったため、補償ができない旨を伝えたところ、保護者が激怒し、説明をした職員を数時間にわたって引き留めて怒鳴り続けたり、送迎の際に担任の職員を引き留めて同様の要求の他「子供が転倒しないように1人職員を張り付かせろ」と要求し、職員らが疲弊していた。
(2)弁護士法人かなめの対応
転倒事故に関して、保険会社に確認をとったところ、お見舞金という形であれば少額であるものの支出が可能であるとの説明を受けたため、まずは園側から、園で発生したことについての謝罪は行った上で、今回の事故についてお見舞金を支払うという形での解決を提案していただいた。
その上で、園児の健全な発育や、職員の人員数から、1対1での保育はできない旨を説明いただき、これで納得できないようであれば、これ以上対応できないことをはっきり伝えるよう助言した。
その結果、お見舞金を受け取ることで納得を得られ、しばらくは職員に嫌味を言うなどの言動はあったものの、その後は落ち着き、通常保育ができるようになった。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
保育事故が発生した際、保護者は冷静ではいられないこともあり、要求が過激になることは珍しくありませんし、園としては保護者の思いには誠実に耳を傾ける必要があります。
しかしながら、その思いを受け入れることと、園としてどこまでの対応をするかは別問題です。
道義的な謝罪をすることは必要ですが、法的な義務があることとないことを切り分けた上で、園としてどこまでの対応をするかの方針を決め、はっきりと伝えることが重要です。
また、園に過失がない場合、損害賠償義務がない以上、原則として保険金が支払われません。もっとも、保険の内容によっては、通院期間や入院期間などによってお見舞金が出るケースもありますので、保険会社に確認することも重要です。
一定の解決金等の支払いにより、保護者の態度が軟化し、解決に繋がることもあります。そして、方針を決めた後は、職員全員一丸となって、決められた対応や回答を徹底することが重要です。どれだけ要求をしても、園としての態度が変わらないとわかれば、徐々にフェードアウトしていく場合もあります。
3−2.事例2:過度な感染症対策を求めるカスハラ事案
(1)事案の概要
感染症が流行していた時期、ある保護者から、「園で使う机のすべてにアクリル板を設置して欲しい」との要求があった。園としては、必要な感染症対策をしていたことから、要求には応じられない旨を伝えたが、これに対して激昂し、「園児の安全をどう思ってるんだ」「子どもが感染症に感染したら責任を取るのか」などと捲し立て、その後も、同様の要求が続いている。
(2)弁護士法人かなめの対応
園の方針として、対応できないことは対応できないとはっきりさせるため、口頭ではなく、書面を出すことを提案し、園名義で文面を作成した。
具体的には、
- 園として取っている感染症対策の内容
- 要求のあった対策については園としては不要と考えており実施できないこと
- 園の方針に不信感があるのであれば、これ以上の対応はできないため、保育の継続が難しいこと
などを記載し、保護者に交付をした。
書面の内容について、何度か架電や面談の要求などがあったが、その後、園児は転園することとなった。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
クレームは、園の運営等に対する貴重な意見であり、原則としては真摯に受け止める姿勢を持つことが重要です。
しかしながら、園の方針決定に介入するような要求については、必ずしも対応すべきではありません。はっきりと、対応ができないことを伝えましょう。
口頭で同様のやり取りが続いている場合には、一度書面で申し入れをすることが重要です。これは、園としての意見を明確にすると同時に、保護者からの執拗な要求が継続していることを示す1つの証拠となり、万が一、園から利用契約を解除しなければならない場合などに重要な証拠となります。
園の方針をはっきり示すことで、言い分が通らないと考えた保護者が、今回のように転園を選ぶケースも少なくありません。仮に、それでも要求が止まらないような場合には、カスタマーハラスメントに詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
また、弁護士法人かなめの代表弁護士 畑山 浩俊が、カスハラに関する具体的な相談事例を紹介しながらカスハラ対応に関して解説した動画も参考にしてください。
4.カスハラ対策の事例
それでは、事業主として職員を守るためにあらかじめ組織としてできることは何でしょうか。
「1.そもそも「カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?」」でも紹介した厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(p18)」によると、以下の4つの取り組みを実施するとよいとされています。
- 1.事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
- 2.従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
- 3.対応方法、手順の策定
- 4.社内対応ルールの従業員等への教育・研修
事業主がカスハラ対策への取組姿勢を明確に示し、組織として従業員を守り尊重するという基本方針を従業員に周知・啓発したうえで、カスハラを受けた従業員が気軽に相談できるよう相談窓口を設置し、カスハラ行為を受けた際には適切な対応ができるよう対応方法をあらかじめ決めて、その対応ルールについて日頃から研修等を通じて従業員への教育を行うというものです。
幼保業界でもこれに沿って以下のような対策を行っている園がありますので、自園での導入を検討してみることを強くお勧めします。
- カスハラ対策指針を作成し、園のホームページに記載する
- カスハラ行為を受けた際やメンタル不調が起きた際の職員の相談対応者を上位者クラス(主任や副園長など)の中で決めておく。
- カスハラ行為への対応ルールを具体例別にQ&A形式でマニュアルとして作成する。
- カスハラ対応専門の講師を招き、職員への園内研修を定期的に実施する。
▶参照:カスハラ研修については、以下の記事で必要性や効果、学ぶ内容、活用方法を事例付きで解説していますので参考にしてください。
5.幼保現場でのカスタマーハラスメントに関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。
- (1)カスタマーハラスメントに対する後方支援
- (2)カスタマーハラスメントへの対応窓口
- (3)研修講師サポート
- (4)幼保事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」
以下で、順番に説明します。
5−1.カスタマーハラスメントに対する後方支援
カスハラへの対応は初動が肝心です。初動を誤ることで、園児や保護者からの信頼を失ってしまうケースもあれば、カスハラの態様をより激化させることもあり、解決が困難となるケースもあります。
最も重要なことは、「ややこしくなってきたから」相談するのではなく、「おや、何か変だぞ?」というタイミングで専門家の意見を仰ぐことです。
そして、相談、回答、実践、反省、というサイクルを回していくことで、園自体にもカスハラ対応への経験やノウハウが蓄積され、組織として成長することができます。
弁護士法人かなめでは、カスハラ対応の初期段階から、現場の責任者から相談を受け、初動からきめ細やかな後方支援を行うことで、円滑なクレーム対応を実現します。
5−2.カスタマーハラスメントの対応窓口
しっかりとカスハラ対策の方針を立て、これに則って対応をしても、どうしてもハラスメントがおさまらない場合や、職員が既に疲弊しており、すぐにでも対応窓口を変えたいという場合もあります。
弁護士法人かなめでは、園では対応しきれないカスハラ対応の窓口となり、交渉等を行います。カスハラの対応を専門家に任せることによって、職員のストレスが軽減し、本来の業務に専念することができます。
5−3.研修講師サポート
弁護士法人かなめでは、カスハラについてその実態、原因から対処方法、予防策まで、園がカスハラに対応していくために必要な知識を身に付けられる「かなめ研修講師サービス」を実施しています。
保育に関する様々な専門的研修とは異なる、カスハラに関連したテーマについて定期的な研修を実施することにより、職員1人1人のカスハラ対応への意識を高め、冷静で適切な対応をとることが可能となります。
実際には、以下のようなテーマで研修を実施しています。
- モンスターペアレントの見分け方
- モンスターペアレント問題が起きる原因
- モンスターペアレントの具体的な事例
- モンスターペアレントへの正しい対処方法
※モンスターペアレント対応のテーマとなっていますが、研修内容は保護者からのカスハラ対応と考えていただいてけっこうです。
カスハラ対応に関する研修については、詳しくは以下のページをご覧いただき、お問い合わせください。
5−4.幼保事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、「(1)カスタマーハラスメントに対する後方支援」をはじめとする、幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。
具体的には、トラブルに迅速に対応するため「Chatwork(チャットワーク)」を導入し、園内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。
そして、弁護士と園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。直接弁護士に相談できることで、園内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
▶参照:幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」については以下をご参照ください。
5−5.弁護士費用
(1)顧問料
- 顧問料:月額6万5000円(消費税別)から
※職員の方の人数、園の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
また、顧問契約をする前に、まずは法律相談をご希望される場合、相談料は以下のとおりです。
(2)法律相談料
- 1回目:1万円(消費税別)/1時間
- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。
※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.Zoom面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
6.まとめ
この記事では、カスハラに対応する意義や、幼保現場でのカスハラの特徴について説明し、幼保現場におけるカスハラの事例について、実際に弁護士法人かなめが対応した事例を紹介するとともに、その対処方法について解説しました。
ここに紹介した事例以外にも、カスハラには様々な種類があり、対応に悩まれるケースも多々あるのではないかと思います。そのため、「保護者からのこの言動はおかしいのではないか?」と疑問を感じた場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
幼保業界に特化した弁護士法人かなめでは、数々のカスハラに関するご相談に対応してきた実績があります。迅速で的確なアドバイスをするだけでなく、場合によっては対応窓口を代行することも可能です。また、カスハラに正しく対応できるような研修の実施や、対応マニュアルの作成サポートも行っています。カスハラへの対応にお困りの園の皆さん、将来的なリスクを考えて対策を検討したい園の皆さんは、ぜひこの記事をご覧いただき、お電話にてご相談ください。
さらに、弁護士法人かなめでは、チャットを使用して、日々の悩み事をいつでもご相談いただける顧問弁護士サービス「かなめねっと」を提供しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応する体制を構築し、幼保業界に精通した弁護士が対応にあたります。「かなめねっと」に興味を持たれた方は、まずはお問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
・更新日:2025年11月26日
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
モンスターペアレント対応、児童保護者との契約に関するトラブル、保育事故、債権回収、労働問題、感染症対応、不適切保育などの不祥事対応、行政対応 etc....幼保現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。
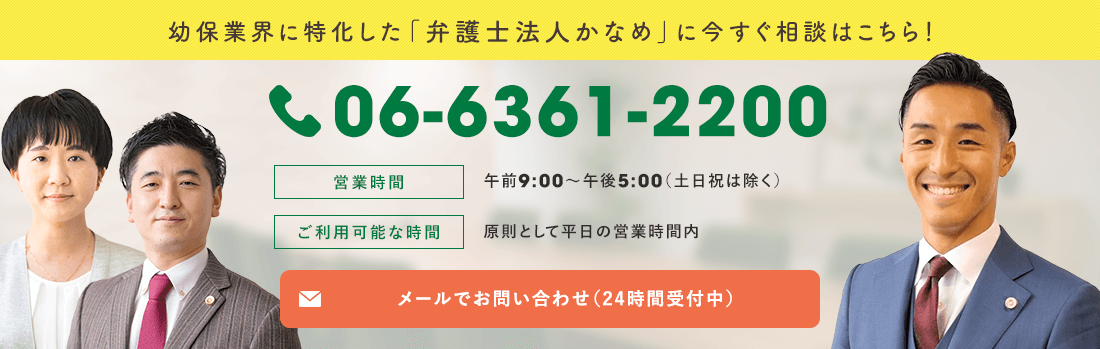
幼保事業所に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。
「かなめねっと」では、弁護士と幼保事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から児童保護者とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!
幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報
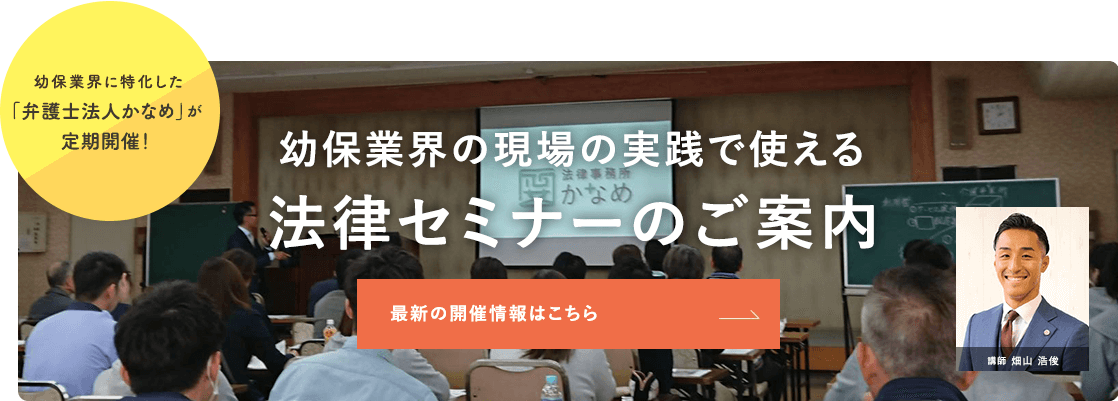
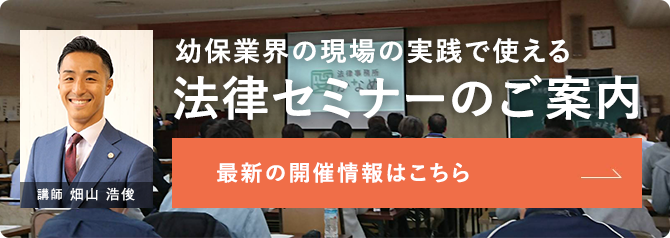
弁護士法人かなめが運営する顧問弁護士サービス「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている幼保事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ幼保研究所」の記事の著者で「幼保業界に特化した弁護士」が担当。
保育園・幼稚園・認定こども園などの経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「児童保護者との契約関連」「保育事故」「感染症対応」「不適切保育などの不祥事対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。
弁護士法人かなめでは、「幼保業界に特化した弁護士」の集団として、幼保業界に関するトラブルの解決を幼保事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に幼保業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
幼保特化型弁護士による研修講師サービスのご案内
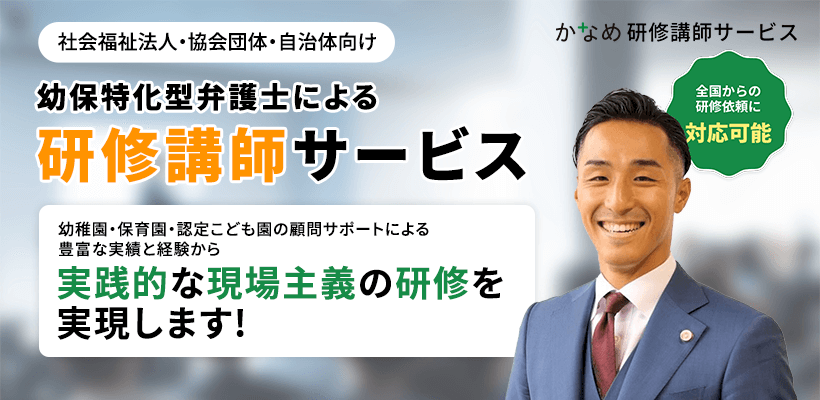
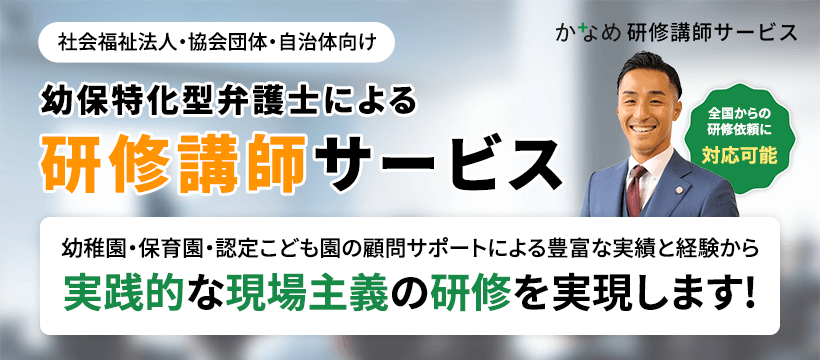
弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの幼保特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の幼保事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「幼保業界のコンプライアンス教育の実施」「幼保業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。
主な研修テーマは、「モンスターペアレント対応研修」「各種ハラスメント研修」「不適切保育・不祥事対応に関する研修」「保育事故に伴うリスクマネジメント研修」「個人情報保護に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、幼保事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。
現在、研修講師をお探しの幼保事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。